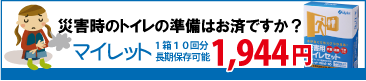 マイレットは水がなくてもスグに使える簡易トイレです。使用後は可燃ゴミとして処理が可能。ご家庭やオフィスで、災害時に備え、ぜひマイレットをご用意ください。 マイレットは水がなくてもスグに使える簡易トイレです。使用後は可燃ゴミとして処理が可能。ご家庭やオフィスで、災害時に備え、ぜひマイレットをご用意ください。
詳しい説明とご購入は>>>こちら |
 お子さまと一緒に楽しく知っていただくために、キッズコーナーを開設しました。アニメーションで水の循環をわかりやすく説明しています。ぜひ、お子さまと一緒にご覧ください。 詳しくは>>>こちら お子さまと一緒に楽しく知っていただくために、キッズコーナーを開設しました。アニメーションで水の循環をわかりやすく説明しています。ぜひ、お子さまと一緒にご覧ください。 詳しくは>>>こちら
|
 |
しずくちゃんマークがついているQ&Aは、平成25年に実施した
お客さま満足度調査で特に多かったお問い合わせです。
|
 |
Q25:法定検査とは何ですか?いつも点検と清掃をしているのに受けなければならないのでしょうか? |

 |
法定検査とは、静岡県の指定する検査機閏から毎年1回受ける事が決まっている水質検査です。
浄化槽は環境汚染の問題に直接結びつく装置なので、環境省より現在の浄化槽が良好な処理をできているかの検査があります。
(法定検査は(財)静岡県生活科学検査センターが行います)
弊社では点検と清掃を通して浄化槽が常に良好な汚水の処理をできるようにしています。
弊社の業務とは趣旨の異なるため、法定検査を受けていただきますようお願いいたします。
■検査機関■(財)静岡県生活科学検査センター
TEL:054-621-5030
法定検査につきましては「Q6」も併せてご覧ください>>>こちら
|
| |
|
 |
Q24:点検と清掃は何が違うのですか? |

 |
浄化槽は、ただ設置されているだけでは汚水の正常な処理はできません。定期点検の際には浄化槽が正常に動いているかを確認することはもちろん、お客さまのお家の状態、季節等の条件に合わせて設定を整えて不具合の出ないように、また、不具合が出ても早期対応ができるようにしています。
そして、トイレや生活の中で出る汚物は浄化槽の中で消えて無くなってしまう訳ではありません。たまった汚れはバキューム車を使い定期的に清掃(くみとり)を行い、し尿処理場へ廃棄します。
浄化槽という装置に対して点検(正常な状態を維持する)と清掃(くみとり)の両方の作業をすることで、初めて汚水の良好な処理ができるのです。 |
| |
|
 |
Q23:浄化槽のフタが割れてしまいました。このままでいいのでしょうか? |
 |
浄化槽タンク内への落下や臭気拡散を防止するためにも、至急新しいフタ(同寸のもの)と交換しますので、当社までご連絡ください。当社では各種のフタを用意しております。
浄化槽のフタはレジンコンクリート(レジコン)製、強化プラスチック製、鋳物製等があり、耐圧の上限(kg)も様々なものがあります。 |
|
| |
|
 |
Q22:浄化槽の周りがたいへん臭います。何が原因なのでしょうか? |
 |
○浄化槽からの臭気の原因として考えられるのは、
・ブロワの異常による機能低下
・浄化槽の清掃不足
・マンホール蓋の密閉が不十分
・抗生剤などのお薬を服用している場合
などがありますが、当社では保守点検の際にこのようなトラブルが発生しないように、浄化槽の周りを含めて点検を行っています。万一このようなトラブルが発生した場合には、お手数ですが当社までご連絡をお願いいたします。管理士がお客さまを訪問し、原因の究明と対応をいたします。 |
| |
|
 |
Q21:契約の名義を変更したり、支払いの方法を変更するのにはどうしたらいいですか? |
 |
当社で保守点検を行っているお客さまは、お電話にて変更手続きを受け付けております。以下の番号にお電話ください。なお、口座振替で料金をお支払いされている方は金融機関の依頼用紙に変更内容を記入する必要がありますので、お早めにご連絡をお願いいたします。
TEL:36-6755 |
|
| |
|
 |
Q20:一時的に転居して住んでいないので、浄化槽の点検の回数を減らしてほしいのですが? |
 |
点検の回数につきましては法律等で決まっています。(詳しくはQ18をご覧ください)
ただし、長期間使用しない場合は浄化槽の清掃を行い、槽内をきれいにしてからブロワを停止させれば、再度使用する時まで点検しないことも可能です。状況を実際にご連絡いただければその都度対応いたします。長期間不在が確実な場合は一度当社までご連絡下さい。 |
| |
|
 |
Q19:以前は5人で住んでいましたが、現在は2人になりました。点検や清掃の間隔を延ばせますか? |

 |
お2人でお住まいとのことですが、浄化槽は人数に係わらず年中無休で動き続けています。
常に、汚水の正常な処理をするためには定期的な点検が欠かせません。
また、浄化槽の法律により一般のご家庭ではお住まいの人数に関係なく4か月に1回以上(年間3回以上)
が義務付けられているため、申し訳ありませんが、人数の増減による回数の変更はできかねます。 |
|
| |
|
 |
Q18:浄化槽の点検は1年間に何回行うのでしょうか?法律で決まっているのですか? |
 |
浄化槽の点検回数は「浄化槽法施行規則」第一章第六条に、「保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。」と定められています。点検の間隔は浄化槽のタイプや大きさ(人槽)によって異なりますが、浄化槽の正常な機能を維持していくためには、期間内に点検を行う必要があります。当社でご契約の皆さまは、この回数に基づいて点検をしております。 |
| |
|
| |
■浄化槽法とはこんな法律です。
浄化槽法第1条の「目的」には以下の条文がありますのでご紹介します。
この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
家庭から出る排水はやがて川から海へと流れていきます。きれいな排水で地球環境を守ること・・・そのために必要な規則や方法について定めたのが浄化槽法です。 |
| |
|
 |
Q17:ブロワは動いているのですが、浄化槽から臭いがします。なぜでしょうか? |
 |
○日頃お使いになっている薬の影響かもしれません。抗生剤などのお薬を使用している場合、浄化槽内のバクテリアが死んでしまうことがあり、臭いが発生している可能性があります。浄化槽内に定期的にバクテリアの促進剤などを投入することをお勧めします。
○曝気(ばっき)状態が弱い可能性があります。曝気が弱ければブロワの修理・交換をお願いします。
○臭気の原因として考えられるのは
1.浄化槽の清掃不足
2.排気設備の不良
3.マンホール蓋の密閉が不十分
4.抗生剤などのお薬を服用している場合
さまざまな可能性が考えられます。浄化槽管理士が伺いますので、ご相談ください。 |
| |
|
 |
Q16:雨の日に風呂場が臭います。浄化槽と関係があるのでしょうか? |
 |
○グリストラップがあれば、そこにゴミがたまっているかもしれません。たまっていたら、それを取り除いてください。
○配管の状態に問題があるかもしれません。水の流れがよくなく雨の日に水が溜まってしまったり臭いが出ているかもしれません。
○浄化槽の排水とその他(浴室・台所等)の雑排水とが合流している枡から臭気が逆流している可能性があります。逆流防止をするためのトラップを取り付けることをお勧めします。 |
| |
|
 |
Q15:ブロワのコンセントが雨に濡れるとトラブルになりますか?またブロワー自体が雨に濡れていますが大丈夫ですか? |
 |
一般的に防雨型のコンセントが設置されていますが、大雨等で水をかぶった場合、漏電によりブレーカーが作動し停止する場合があります。ブロワーは通常の雨には対応できるように設計されていますが、ブロワーの設置場所によりますが、雨どいにより雨水が排出される付近に設置された場合や豪雨などによりブロワー内に水が入り故障の原因になることがあります。 |
|
|
 |
Q14:浄化槽に投入している薬剤はどのようなものですか? |
 |

|
●消毒剤:
処理された水を塩素消毒する際に使います。浄化槽で処理された水は微生物の働きできれいになっていますが、大腸菌や病原菌は分解されないため、外の川や側溝に流す際には減菌させる必要があります。
|
| |
●殺虫剤:
粒剤とプレート剤があります。粒剤は、蚊の幼虫(ボウフラ)やハエの幼虫(ウジ)の防除のため使用します。またプレート剤は、プレートから薬剤が蒸発して浄化槽内に広がり、成虫を駆除します。 |
| |
●消臭剤・機能促進剤:
1.抗生剤などのお薬を飲んでいる方がいるご家庭
2.ブロワーが故障し浄化槽内が酸欠状態になった時
3.正月やお盆、お祭りなどで一度に大勢の人がトイレを使用したとき
1〜3のような原因で浄化槽に負荷がかかった状態の時、高活性バクテリアの配合された悪臭を防止する機能促進剤を使用します。 |
| |
●消泡剤:
1.トイレ洗浄剤を多量に使ったとき
2.新設して間もない浄化槽
3.清掃の直後
4.抗生剤などのお薬の服用によって
1〜4を主な原因として浄化槽内に泡が発生した場合に、発生した泡を消すために使用する薬です。 |
| |
|
 |
Q13:浄化槽の上を駐車場にしたいのですが、車を停めてもいいですか? |
 |
1.以前からある浄化槽の上に車を停める場合
そのままでは浄化槽本体が車重に耐えることができないため、亀裂が入ったり破損することがあります。またマンホールの蓋が壊れることもあります。
以前からの浄化槽の上に車を停める場合には、浄化槽本体の周りを補強する工事が必要です。あわせてマンホールも耐荷重用のものに取り替えます。
2.新しく浄化槽を設置する場合
始めから浄化槽の上を駐車場にする場合には、それに耐えられる型式(支柱工事不要)の浄化槽を設置してください。
※支柱工事不要の浄化槽の場合、最大荷重は2t(2000kg)までです。 |
 |
| |
|
 |
Q12:トイレでたくさんの水を流すと、浄化槽に影響がでますか?(例えば音消しのため) |
 |
浄化槽は微生物の働きにより排水をキレイにする装置なので、一度にたくさんの水を流すと微生物の処理能力が追いつかず臭いの発生する原因になります。
また流入する水の勢いで浄化槽内に堆積した汚泥が外に流れ出す可能性があります。
トイレだけでなくお風呂や台所の排水も処理する合併浄化槽の場合には、「お風呂の水を流しながら、洗濯機を動かし、台所で洗い物をする…」などいっぺんに水を流すことがないように排水の時間の調整していただくことをお勧めします。 |
 |
| |
|
 |
Q11:再生紙でできたトイレットペーパーを使用してもいいですか? |
 |
JIS規格のトイレットペーパーであれば再生紙でも構いません。
※トイレットペーパー以外の紙類はトイレに流さないようにしてください。トイレの詰まりや浄化槽の機能低下につながります。 |
 |
| |
|
 |
Q10:海外赴任で長期不在になります。ブロワーの電源は入れておかないといけないですか? |
 |
ブロワーは浄化槽内の微生物に必要な空気を送る装置です。そのため電源を入れておけば、常に微生物が働きますので、浄化槽内から臭いも漏れず、帰国してもすぐに使うことができます。
ただし、どうしても電源を切る場合には、一度浄化槽内を清掃して槽内の水を張り替えることをお勧めします。 |
| |
|
 |
Q9:ブロワーと水中ポンプの違いは何ですか? |
 |
■ブロワー
浄化槽内の排水をきれいにする微生物(好気性微生物)に必要な空気を送る装置です。そのためブロワーが動いていないと、この微生物の活動が弱まり排水の浄化ができなくなり、悪臭の原因になります。
■水中ポンプ
小型浄化槽の場合:浄化槽内で処理された水を、外の川や側溝に排水する装置です。浄化槽から川や側溝までの距離があったり、勾配が不足して水が自然に流れない場合にポンプを設置して強制的に排水します。
大型浄化槽の場合:原水槽から調整槽や、ばっ気槽から沈殿槽など槽の間で汚水や処理水を送る装置です。 |
 |
| |
|
 |
Q8:家族2人住まいですが、浄化槽の大きさが5人槽となっています。
どうしてでしょうか? |
 |
浄化槽の大きさは、お住まいになっているご家族の人数ではなく、「人槽」又は「処理対象人員」という単位で表されます。処理対象人員の計算方法は、日本工業規格として定められていて、一般的に住宅の延べ床面積により次のように分類されます。
住宅の延べ床面積:130平方メートル未満を小家族用として5人
住宅の延べ床面積:130平方メートル以上を普通住宅用として7人
この基準は建物を例えば二世帯住宅など用途別に分類して、それぞれについて建物の床面積などにより細かく人員の計算方法が示されていています。つまり、浄化槽の大きさを示す「人槽」は建物の建坪で決まります。建物が大きければ、住んでいる人、使用している人が少なくても浄化槽の「人槽」は大きくなります。 |
|
| |
|
 |
Q7:浄化槽内におけるバクテリアの効果というのはどのようなものですか? |
 |
浄化槽の中にはたくさんの微生物が繁殖しています。この微生物が有機物を分解する働きを利用して、汚水をきれいにするのが浄化槽の仕組みです。 |
|
|
 |
Q6:浄化槽検査のハガキが来ました。どうしたらいいのでしょうか? |
 |
浄化槽には法律で義務付けられた検査が2種類あります。浄化槽法の7条で定められた検査と11条で定められた検査で、一般的には「7条検査」「11条検査」と呼ばれています。
■7条検査(浄化槽を新たに設置した時:1回のみ)
浄化槽使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に受ける検査です。この検査は浄化槽の設置工事等・保守点検が適正に行われているかをチェックします。
■11条検査(毎年)
7条検査実施1年後から毎年1回受ける検査です。浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ浄化槽の機能に問題がないかをチェックします。
なお、この検査については指定された機関が行うことになっておりますので、詳細につきましてはハガキの送り先にお問合わせいただきますようお願いいたします。 |
| |
|
 |
Q5:保守点検の記録は保存しなければいけないのですか?何をどう保存しておけばよいのでしょうか? |
 |
浄化槽管理士が皆さまの浄化槽を点検した際にお渡しする「保守点検報告書」を必ず保存してください。この保守点検報告書はいわば患者のカルテにあたるもので、医師がカルテを見ながら患者の状態を把握して、適切な治療を行うのと同じように、保守点検報告書は浄化槽の管理状態が一目で分かる大切な記録です。また、浄化槽法第5条では、この保守点検報告書を、3年間保存することが義務付けられています。浄化槽の法定点検(十一条検査)の際には保守点検報告書が必要となりますので、ご家庭や事務所で専用の書類入れを作って保存してください。 |
 |
| |
|
 |
Q4:カビ取り剤などの掃除用洗剤は使用しても大丈夫ですか? |
 |
市販のカビ取り剤のほとんどが、次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしていますので、大量に使えば浄化槽内で働く微生物を殺してしまいます。ですから、カビ取り剤は適正量を使用し、その後は多めの水で洗い流してください。また、その後は1ヵ月に1度、薬用アルコールを霧吹きでタイルに吹き付ければ消毒とカビの発生を防ぐことができます。 |
 |
| |
|
 |
Q3:清掃はどうしてもやらないとならないでしょうか? |
 |
浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条により1年に1回以上行うことが義務づけられていますが、清掃の時期は浄化槽管理士が法令の清掃周期と浄化槽が必要とされている浄化槽能力を下回ることがないように判断して行います。
浄化槽法第十条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
(浄化槽管理者とは一般的に浄化槽の所有者・占有者を指します。) |
清掃を行わないでいると浄化槽内に汚物が堆積して次のような現象を引き起こす恐れがあります。
●浄化槽が詰まって家の中から排水が流れなくなったり、汚水がマンホールからあふれ出します。
●浄化槽で処理できない排水が汚水のまま川や側溝に流れ出して悪臭の原因になります。
●大腸菌などの細菌が処理されず浄化槽外に放出されたり、虫やハエなどが発生しやすくなります。
●浄化槽本体に負荷がかかり、内部の破損や機能の低下を引き起こします。
当社では浄化槽管理士が皆さまの大切な浄化槽をこまめに点検し、上記のような現象が起こらないように清掃を行っています。
|
| |
|
 |
Q2:トイレ洗浄剤を使用すると、浄化槽の故障の原因になりますか?(トイレ洗浄剤とはタンクの上に設置して便器を洗浄するものです。) |
 |
トイレ洗浄剤の使用により、浄化槽の故障の原因になることはありません。詳しくは使用するトイレ洗浄剤の取扱説明書をお読みください。 |
| |
|
 |
Q1:清掃してまだ日が経っていませんが、虫が出ています。どういうことですか?
|
 |
浄化槽の清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥(堆積物)を汲み取ることですので、虫を完全に取り除くことはできません。清掃後に虫が発生するのは汲み取りをしても浄化槽の中に虫の卵が残っていて、そこから孵化するためです。殺虫剤の使用で、虫の発生を抑制することができます。
・ご希望により有料にて殺虫プレートを設置いたします。
お気軽にお問合わせください。 お問合わせはこちら>> |
 |



